2024年度
五十音順
掲載内容は2024年時点のものです。

石塚 晴日
いしづか はるひ
舞台芸術制作者、俳優/ぺぺぺの会
■受講を終えて
日々忙しなく過ごしていると、自身の活動の根本や日頃課題に感じていることを思い過ごしがちですが、月一回の受講の度に、それらにじっくりと向き合う機会をいただきました。講座を受けることで多角的に分析でき、思考を深めることができました。受講生同士で話し合い、交流し、異なる意見や考えを共有できたことも貴重な経験でした。
受講の時間も、それ以外の時間も、受講生それぞれが「私には何ができるか」という視点で他者や事象と関わり、自分にできることを相手に与えたいという意思や行動が、環境をより良いものにし、未来を変えていくのだと思います。皆さんのgiverの精神にリスペクトです!
■レポートタイトル
協働を生み出す評価の実践

遠藤 ジョバンニ
えんどう じょばんに
ライター/合同会社きゅうり
■受講を終えて
受講を終えて、自分に訪れた心境の変化や気づきなど「変わったこと」もたくさんありました。しかし、講師の方々やファシリテーターのお二人の機知に富んだ話、他の受講者の意見を受けて、炙り出されるように自分のなかにある「変わらないもの」の言語化も非常に進んだと思います。長期間にわたり、本当にありがとうございました。
■レポートタイトル
自分のために、“わらじ”を二足、あたためておく

川嶋 信子
かわしま のぶこ
琵琶奏者/洗足学園音楽大学 非常勤講師、琵琶ひとひら会 代表、まなびわ信絃会 主宰、日本琵琶楽協会 会員
■受講を終えて
過去にこの講座を受けた友人達は、実践力のある尊敬できる友人で、ならば私も受けようと、締め切りギリギリに駆け込んだ。私を選んで下さった事に改めて感謝申し上げたい。
が、最初は「キャパシティビルディングって何? 募集要項にも難しそうな事が書いてあるなぁ」というのが正直な印象だった。しかし、とにかく実演家としてある一定の関わりのなかにいたのでは解決できない問題がある、という危機感があった。表現を極める事だけを見つめ続ける。そういう生き方が理想的だが、マイナーな分野はそれだけでは立ち行かないのだ。正直なところ、まだ何も解決できていないが、この講座のお陰で考え続ける耐久力は身に付いたと思う。そして困ったときには相談できる場を得た事も大きい。一人じゃない、そう思えた講座だった。
■レポートタイトル
琵琶が生かされる場を求め、つくる
~日本の音と声を遺すために~

葛木 英
くずき あきら
劇作家、演出家、俳優、講師/Stage Connect 代表
■受講を終えて
講座を終えて感じるのは、「創る」ことを仕事にしてきた自分が、今最も関心を持っているのは「社会と演劇をつなぐ」ことではないかということです。創作においても、現在取り組んでいる映画で児童の貧困問題を伝えることや、フォーラムシアターを通じて社会課題と向き合うことに強く惹かれます。また、未来の創作家を育成するうえで、芸術家が社会のなかで生きていくためのライフプランをどう描くべきかという課題を改めて実感しました。
舞台のみで生計を立てられる人はごく一部であり、多くの専門職が経済的な理由で業界を離れている現実があります。公演を継続するには助成に頼らざるを得ない状況も多く、演劇の持続可能性について考えさせられました。本講座を通じて、演劇が社会のなかでどう存続し、発展していくべきかを深く考える機会となりました。
■レポートタイトル
現実を変えるために、リハーサルをしよう!
―フォーラムシアターによる企業研修・地方創生・演劇教育の可能性

篠原 美奈
しのはら みな
アートマネージャー/「あちらこちら」主宰
■受講を終えて
「私もけっこう偏った考え方をしているんだなぁ……」と思ったのが一番の感想かもしれません。アカデミアに飛び込んで早8年。社会と接するタイプのアートに関わってきたとはいえ、知らず知らずのうちに「芸術とはこうあるべき」という像が狭まってしまっていたのではないかと思いました。自身の活動や業界をより良くしていこうと志を同じくした受講者のなかでも、これまでの経験や今立っている状況はさまざまで、自分が全体のどの辺にいるのかを初めて肌感覚で掴めたような気がします。今は自分のことで精一杯だけど、目の前のことを一つずつ悩みながら積み重ねていくことが、きっと10年後の自分につながり、私が健やかであることそれ自体が業界のより良い未来にもつながるんだと、そう感じさせてくれるような時間でした。素敵な機会をありがとうございました!
■レポートタイトル
わたしたちは音楽で「ほどいて、ひらいて、軽やかに結ぶ。」
―「〇〇じゃない」から「〇〇をつくる」という自分たちを軸としたミッションへ―

白井 莉奈子
しらい りなこ
独立行政法人国際交流基金 文化事業部 美術チーム 主事
■受講を終えて
多様な芸術分野で、こんなにも真剣に悩んで、考えている人がいると知ったこと。そして、そうした人たちに出会え、議論を重ねた時間が、「私もがんばれるかもしれない、がんばりたいな」と、「自分が信じる未来があるなら見てみたい」と思わせてくれた気がします。
「芸術は必要か」という問いに、受講生の松田さんが答えた「芸術は社会にとっての基礎研究のようなもの」という言葉は、ひっかかることなく私の心に重さを持って入ってきて、作曲家の森さんの案内で行った現代音楽のコンサートでは、こんな世界があるんだと、知らなかった景色が見えた気がして、中村先生の講座で「文化の民主主義」という概念を知ったときは、その考え方を言語化した人がいるという事実に私は後押しされている気がして。たくさんのことが心に刺さって、溜まっていくような時間でした。
■レポートタイトル
アフリカとの文化芸術交流の活性化を目指して
ージンバブエを起点にー

新谷 昂大
しんたに たかひろ
会社員/劇団ZERO-ICH 制作
■受講を終えて
本講座は大変に刺激的であった。第一線で活躍されている講師陣による講義、多彩な参加メンバー、そしてもたらされる正解のない問い──。この講座が終わってしまう寂しさを感じたのは言うまでもない。
最終日。少なからずの参加者が、“コトバ”という単語を使っていたことが印象に残っている。自分の“コトバ”を磨く、“コトバ”で伝える、“コトバ”を探す。そういった表現が多く出てきたように思う。ここに何か、生きていくことに対する本質的な何かがあったような気がする。
本講座を通して得たものは、自身や活動を通して社会に還元したいと強く思う。そして何より、「あ、自分って芸術がわりと好きなんだな」と日々に埋もれていた感情を再び呼び起こしてくれた、この講座に関わった全ての人々にこの場を借りてお礼を申し上げたい。
■レポートタイトル
演劇業界経験ゼロの人が、スタッフワークをイチから学べるか?

野村 善文
のむら よしふみ
株式会社 PortPort 代表取締役
■受講を終えて
キャパシティビルディング講座、ありがとうございました。自分自身、制度設計や仕組みづくりに関わるなかで、制度を届ける先の人々と遠くなることが多くなるのを悩んでいたので、さまざまな取り組みをされている人たちと立場関係なく、意見を交換しながら自分自身の常識を疑ったり、立ち止まったりすることができる機会がとても有益でした。この取り組みが長く続き、さまざまな人にとって必要な知識やつながりを生み続ける場所であることを願います。
■レポートタイトル
ツーリズム事業について

古澤 百花
ふるさわ ももか
東京大学経済学部3年生/第7回、8回新世代賞実行委員長
■受講を終えて
助成金の申請がうまくいかず、藁にもすがる思いでキャパビル講座の案内を見つけ、応募しました。いざ講義に参加してみると、内容は必ずしも助成金申請に直結するものばかりではありませんでした。中村さんの講義で学んだ「抽象のはしご」を通してキャパビルで得られる学びはまさに「抽象」であると感じました。そして、若林さんが最後におっしゃっていた「キャパビルで学んだことは、時間が経ってから活きてくる」という言葉がしっくりきました。助成金申請という差し迫った課題に直面して参加したキャパビル講座でしたが、振り返ってみると、具体的なノウハウを学べる講座はアーツカウンシルのなかに他にも多くあります。そんななかでキャパビル講座に出会えたことは、むしろ将来のキャリアを考える上で大きな意味を持つものになりました。半年間、寛大に受け止めてくださり、本当にありがとうございました。
■レポートタイトル
若手アーティストの支援とアート業界の若手人材の育成
~「新世代賞」の運営を通して~

本多 麻衣
ほんだ まい
豊島区役所 文化商工部 文化デザイン課 会計年度任用職員/フリーランス テレビ番組制作補助
■受講を終えて
映像業界から文化行政の世界へ来て、気づけば8年。行政の立場にいると、文化関係者のつながりが少なく寂しさを感じている時期でした。
講座を通じて、素敵な受講生たち、若林さん、小川さん、講師の皆さん、アーツカウンシル東京とON-PAMの皆さんとつながれたことは、これからの人生の財産にしたいと思っています!!
また今回、制作の現場でのケアやサポートが、いかに大切かということを学ばせて頂きました。是枝監督の活動のように、文化全体においてもサポートをしっかり行える組織体をつくらなければ、文化は継承できないと感じています。改めて文化行政という立場で若い世代へ明るい文化の未来を考えていきたいと思います。本当に貴重な学びと出会いの時間をありがとうございました!!!
■レポートタイトル
「360度対話の場」
~民なでつくるNEW文化政策~

松田 愛子
まつだ あいこ
多摩美術大学 社会連携部社会連携課
■受講を終えて
各講座の内容が、自分の課題意識にヒットするものだったことはもちろん、それぞれのテーマの「そもそも」の話をとても整理された状態で聞くことができて、毎回発見のある、改めて学びの楽しさを感じることのできる時間でした。特に中間ディスカッションの回で伺い、話し合った「非営利とは何か」「公共性とは何か」というテーマは、それまでの講座を総括するものとして、考え方の道筋を得られたような感覚がありました。さまざまな領域で活動する意欲的な受講生のみなさんと一緒に講義を聞いて、喋って、そして書いてまとめることで、少し前に進めたような気がしています。これからも縁のできたみなさんの活動に刺激を受けながら、自分の活動をより良くすべく、取り組んでいきたいと思います。
■レポートタイトル
アーティストの活動を支えるインフラをつくる
「Up & Coming」と大学間連携

松永 かおり
まつなが かおり
東京都世田谷区立砧南中学校 校長/全国造形教育連盟 委員長/東京都中学校美術教育研究会 副会長/独立行政法人国立美術館の教育普及等に関する委員会 委員
■受講を終えて
目の前の仕事に埋没してしまいがちなので、自らに刺激を与え新しい知見を得ること、新しい人脈をつくることを目的として受講にチャレンジしました。小川さん、若林さんをはじめとした素晴らしい講師の先生方のご指導、他の受講生の皆さんの熱あるディスカッション、そしてスタッフの皆様の細やかなご準備やご配慮のおかげで、漠然としていた自分のやりたいこと、やるべきことが明確になり、確実な次へのステップを見つけることができました。貴重な経験をさせていただき心から感謝いたします。
■レポートタイトル
芸術教育の価値創造に向けて

モスクワカヌ
もすくわかぬ
劇作家/劇作家女子会。メンバー、劇団劇作家 所属、noo主宰
■受講を終えて
受講する前、申し込んだはいいものの不安でいっぱいでしたが、始まってみると楽しくてあっという間の半年間でした。興味関心があることだけでなく、思いもよらないことや一人ではアクセスできなかったであろう考え方に触れられたことも、とても貴重な学びの機会だったと思います。また、キャパシティビルディング講座2024の「場」自体も、運営関係者の方々が参加者の安心や安全に配慮しているということが感じられ、その心配りに助けられました。困ったときにはサポートを受けられるという信用を「場」におけることで安全を感じられ、困りごとの多い自分でもパフォーマンスを発揮しやすかったと思います。
この講座に参加し完走できたことは、私にとっては大きな財産です。関係者の皆様に感謝いたします。
■レポートタイトル
『稽古場をケアする』
―創造の「場」としての安全性と持続可能性

森 紀明
もり のりあき
作曲家/一般社団法人Cabinet of Curiosities 代表理事
■受講を終えて
私は現在、経済的に自立しにくい芸術音楽の領域で主に活動していますが、ポップ・ミュージックや劇伴など商業音楽で活躍する知人も多く、営利・非営利を問わず、どちらの活動も社会にとって欠かせないものだと確信しています。一方、資本主義社会のなかで、非営利アートから直接的に恩恵を受けていない人々を説得し、吉本光宏氏の言う「サイレント・パトロン(公立文化施設の存在や活動を支持する市民層)」を増やしていくことは、公的支援の拡大や共感者の獲得につながり、非営利アート活動が持続するためにも大切なことだと考えています。受講を通じて学んだ知識や方法論は、そのための大きな力になると実感しています。さまざまな芸術分野で活躍する受講生たちとの出会いも、これからの活動にとって貴重な財産です。この機会に心から感謝しています。
■レポートタイトル
「現在形の芸術」としての音楽創造環境のデザイン

森田 諒一
もりた りょういち
演劇チーム「あくびがうつる」メンバー
■受講を終えて
どんな時間だったのか? さまざまな思考をインプットしていく、脳のなかがグツグツ煮えたぎる感じ。出会う場所として、素晴らしい体験をする。私たちは、さまざまな課題に向けて力を合わせていけないだろうか? これからあとどれぐらいの時間が、わたしたちに残されているのだろう。考えなくてはいけないことをすべて考えていかなくてはならない。わたしにとっては、百年後や千年後に、アートがどうなっていくのか?ということだった。
この講座の受講生はもうすでに100人以上いるのだという。100人が別の100人と出会えば、出会いの線は倍々に増えていく。わたしは、ここで夢を語った。恥ずかしげもなく。マグマのような熱いものが、冷えて形になっていく。その無数の形は、ある川の流れの先で誰かが偶然みつけるいろんな形の石なのだ。たぶん。
■レポートタイトル
ことばにしていく実践
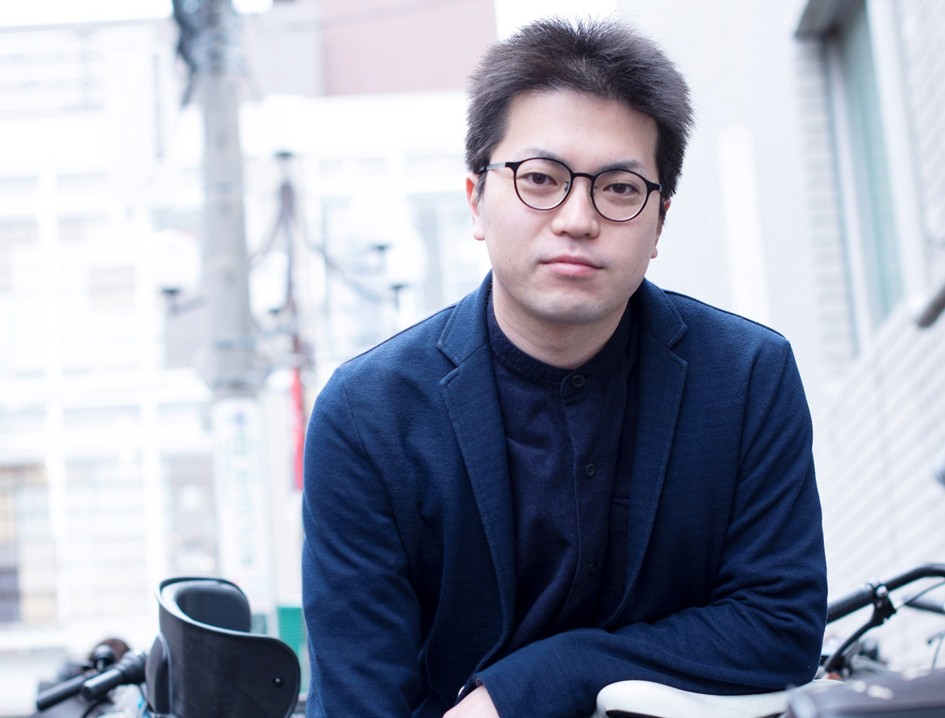
山本 タカ
やまもと たか
劇作家、演出家、脚本家/劇団「くちびるの会」代表
■受講を終えて
第4回講座に、講師でいらして下さった久保田さんが、オフラインでの質疑応答の中、ぽろっとおっしゃった一言が僕は忘れられません。
「アートが、アートだけで自立しないのは、もうみなさん活動されているから、わかってると思いますが……」
これは映像にも残っていないので、僕の記憶のなかだけにある言葉です。
もちろん、社会の一員である劇団主宰の山本タカは「わかっていた、つもり」でしたが、久保田さんこの言葉を明言されたあの瞬間、僕の心に必死でしがみついていた、もう一人の僕、ゲージュツカの山本が「ですよね」と、なんだか、白旗を上げた感覚がありました。
歴史を振り返ると、そうでした。じゃあ、これから、僕はどうするのか?動きながら、考えます。考えて、動くのではないのです。まず動き、それから考えるのです。
と、宣言してみます。
■レポートタイトル
「こんどのおやすみは、おしばいをみにいくの」
キャパシティビルディング講座2024
ダイジェスト動画







